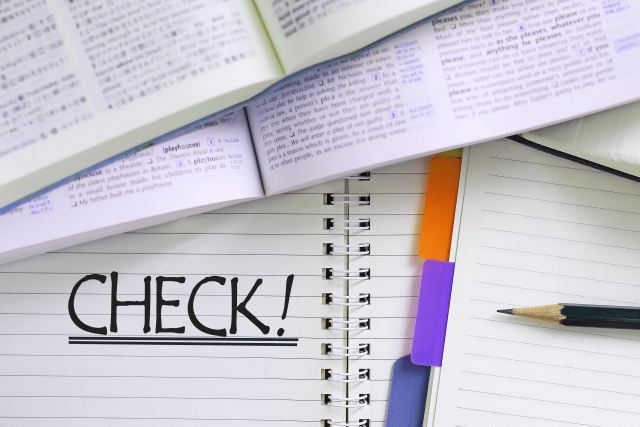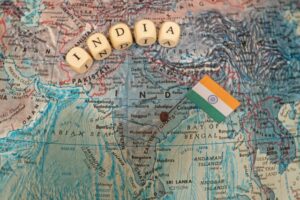はじめに:安全距離の「ものさし」が変わる
2024年11月、機械安全の重要な国際規格であるISO 13855 が14年ぶりに改訂されました 。この規格は、ライトカーテンなどの安全装置をどこに設置すれば危険から作業者を守れるか、その「安全距離」を計算するためのルールブックです。
今回の改訂は、協働ロボットや無人搬送車(AGV)が人と共存する現代の生産現場を反映した、根本的な見直しです。この記事では、この重要な改訂のポイントを、初心者にも分かりやすく解説します。
1. なぜ改訂されたのか?静的から動的へ – 思想的転換
旧2010年版は、機械が柵で囲われた「静的な」環境を前提としていました 。しかし、協働ロボットやAGV が普及した現代では、危険源自体が動く「動的な」環境が主流です。旧規格では、こうした動く危険源に対する安全を十分に確保できませんでした。
この変化に対応するため、新2024年版では安全設計の思想が「静的防護」から「動的防護」へと大きく転換されました。この思想転換は、安全距離の基本式に明確に表れています。
- 2010年版の基本式 (旧):
$$S=(K×T)+C$$
- 2024年版の基本式 (新):
$$S=(K×T)+D_{DS}+Z$$
新規格では、機械自身の動きも考慮する画期的な概念が導入されました。
ここで「DDS」とは保護装置による到達距離を指し、ガードやライトカーテンなど、保護装置によって考慮が必要な追加距離を意味します。
2. 最重要変更点 -「動的分離距離」という新概念
2024年版が導入した最も重要な概念が「動的分離距離(Dynamic Separation Distance)」です。
- 静的分離距離(旧): プレス機のように危険源が固定されている状況を想定します。
- 動的分離距離(新規): AGV のように危険源自体が動く状況を想定します。人がAGV に近づくだけでなく、AGV も人に近づいてくるという、両者の接近を考慮して安全距離を計算する必要があります。
この考え方を数式に反映したのが、新たに追加されたパラメータ「SM」です。
$$S=(K×T)+S_M+D_{DS}+Z$$
「SM」は「安全装置が作動してから機械が停止するまでの間に、機械(危険源)自身が移動する距離」を意味します。つまり、AGVが検知されてから完全に停止するまでの間に進んでしまう距離も、安全距離に含めなければならない、という考え方です。
2024年度版では、この「SM」計算するための具体的な式も提示されています。特に、機械の加減速度が既知で一定の場合、以下の式を用いて計算すると定められています 。
$$S_M=v_0 \times T−\frac{d}{2} \times {t_M}^2 + \frac{a}{2} \times {t_{SRP/CS}}^2$$
ここで、「V0」は機械の初速度、「d」減速度、「a」は加速度、「tM」は機械的慣性に関する時間、「tSRP/CS」は安全関連制御システムの応答時間を示します 。この式により、AGVなどの動的な危険源の挙動をより精密に安全距離の計算に組み込むことが可能になります
この動的防護を実現する核心技術が、速度・分離距離制御(Speed and Separation Control, SSC)です。これは、自動車のアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)のように、人と機械の距離を監視し、距離に応じて機械の速度を能動的に制御する技術です 。
3. 対象安全防護の拡大と要件の厳格化
今回の改訂では、個別の安全装置に対する要求も大幅に更新されました。
3.1 インターロックガード (Clause 12)
旧版ではごく僅かだった記述が大幅に拡充され、「ガードロックなし」と「ガードロックあり」で明確に計算式が区別されました。
- ガードロックなし: ガード(扉)を開け始めた際の隙間からの到達を具体的に計算することが求められます。
- ガードロックあり: 機械が停止するまでガードが施錠されている時間を計算に利用でき、安全距離をより現実に即して最適化できる可能性があります。
表1: インターロックガードの安全距離計算:新旧比較
| 保護装置の種類 | 2010年版 (ISO 13855:2010) | 2024年版 (ISO 13855:2024) | 主な考慮事項 |
| ガードロックなし | 限定的な記述のみ。具体的な計算式は示されず、一般的な原則に留まる。 | $$S = (1600 \times T) + D_{GT}$$ | ガードが作動するまでの隙間 「e」からの到達距離 「DGT」をISO 13857に基づき計算する必要がある。 |
| ガードロックあり | 規定なし。 | $$S = K \times (T – t_{DY}) + D_{GT}$$ | 機械停止までのロック時間 「tDY」 を考慮でき、安全距離をより現実に即して最適化できる。 |
3.2 片手/足操作制御装置 (Clause 11)
片手または片足で操作するスイッチが、新たに対象として追加されました。非常に大きな安全距離が要求されており、これは操作中でない方の手足が危険源に到達する最悪のシナリオを想定しているためです。
3.3 両手操作制御装置 (Clause 10)
到達距離のパラメータが大幅に厳格化されました。
- 2010年版: 侵入距離
$$C = 250 \ mm$$
- 2024年版: 到達距離
$$D_{DS} = 550 \ mm$$
この変更は、作業者が片手と反対側の肘などでスイッチを押し、安全機能を無効化する誤使用のリスクを考慮したものです。この 550 mm という数値は「肘から指先までの長さ」を根拠としており、多くの既存設備で制御盤の移設が必要になる可能性があります。
4. その他の重要な改訂点
- 用語と計算式の明確化: 旧版の「最小距離」は「分離距離」に、包括的だった「侵入距離 「C」は「到達距離 DDS」と「補足距離係数 「Z」 に分割されるなど、用語がより厳密になりました。
- 全身アクセスと不意の再起動防止: 安全柵の中など、人が全身で進入できるエリアで、エリア内からリセットボタンを押して機械を再起動させてしまう事故を防ぐための要件が強化されました。
- 段差やプラットフォームへの対応: 工場内の段差などを考慮した、より現実的な安全距離計算のルールが定められました。
結論:新 ISO 13855 へ適応するための実践的ステップ
ISO 13855:2024 への改訂は、機械安全の設計思想における大きな転換点です。この新しい「ものさし」に適応することは、今後の機械設計における必須要件となります。
設計者・管理者のための実践的チェックリスト
- 動的ハザードの再評価: 自社のAGV や協働ロボットについて、「動的分離距離」を考慮したリスクアセスメントを再実施する。
- 全インターロックガードの監査: ガードロックの有無を確認し、新しい計算要件を満たしているか検証する。
- 両手操作制御盤の距離測定: 新しい到達距離 DDS=550 mm の要件を満たしているか確認し、必要であれば移設を検討する。
- 設計標準・ツールの更新: 社内の計算ツールやガイドラインを新しい計算式と用語に更新する。
- リセットボタン配置の見直し: 全身アクセスの可能性がある設備で、防護エリア内からリセットボタンに手が届かないかを確認する。
今回の改訂は、一見すると要求が厳しくなったように感じられるかもしれませんが、より安全で生産性の高い機械システムを実現するために不可欠な進化です。
インテリスク株式会社では、新規格へのスムーズな適応を支援する専門的なサービスやリスクアセスメントを提供しています。この記事が皆様のお役にたてば幸いです。